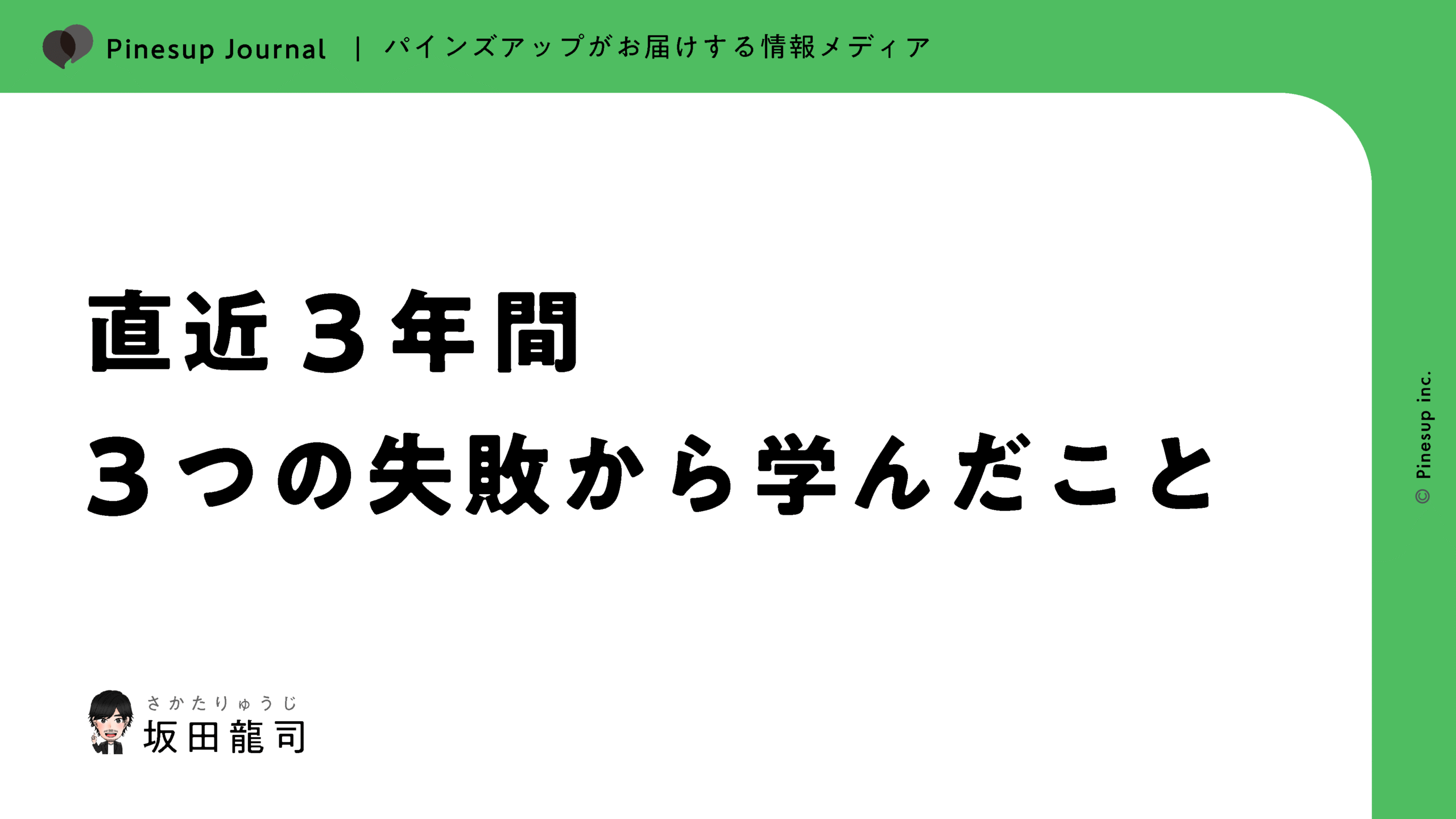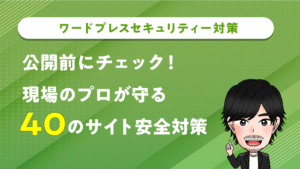私たちパインズアップは、ありがたいことに多くのお客様とご縁をいただき、地域の事業を支えるホームページやデザイン制作に取り組んできました。
ですが、すべてが順調だったわけではありません。毎回、全力で取り組んでいるつもりでも、「うまくいかなかったな…」と感じたことや、「自分たちの力不足だった」と反省する場面がありました。
ここでお伝えするのは、そんな失敗の記録です。
誰かに責任を押しつけたいわけでは、けっしてありません。どんな出来事にも、私たちに改善すべき点があったと受け止め、そこから何を学び、どのように社内で仕組みを変えてきたか。その過程を共有したくて、この記事を書きました。
今回は、直近3年間の中でも特に学びの大きかった3つの事例をご紹介させていただきます。
相見積もり10社からのリード獲得
▶ 何があったか
ある相見積もり系のマッチングサイトから、お問い合わせをいただきました。
10社以上が提案を出す中で、私たちの提案や姿勢を評価していただき、制作パートナーに選んでいただけたことは、とても嬉しく、期待も大きかったです。
しかし、制作が進むにつれて「段階的に公開してほしい」「この追加は費用内でお願いしたい」といったご要望が次第に増えていきました。最終的には「メールが届かないから納品されていない」といった理不尽なご指摘まで受けることとなり、結果としてプロジェクトは円満に完了することができませんでした。
▶ 何を学んだか
最も大きな気づきは、「寄り添う=何でも応える」ではない、ということです。
当時は、選んでいただいたことへの感謝が強すぎて、「断らないこと」が誠実だと思い込んでいました。けれど、それは結果的に、お互いの信頼を削ることにつながってしまいました。
この経験を通じて、私たちの中で「期待に応える」と「期待に飲まれる」は違うという認識が生まれました。
現在では、案件の初期段階で「私たちにできること・できないこと」を整理し、ドキュメントにして共有する仕組みにしています。
- 契約時点で、対応できる範囲を明確にする
- 要求が広がりそうな場合は、事前に線引きを共有する
- 「何でもやってくれる御用聞き」にならないよう、社内ルールを明文化する
これらを徹底したことで、それ以降の案件ではトラブルが大きく減り、クライアントと対等な信頼関係を築くことができるようになりました。
納品直前の大幅な仕様変更
▶ 何があったか
工程ごとに確認を取りながら進めていた案件で、納品直前に「やっぱりここを変えたい」と大幅な修正依頼が入りました。
理由をうかがうと、新たに配属された部門責任者が確認した結果、「全体のイメージが違う」とのこと。
結果として、
- デザインの修正
- テスト環境での再構築
- 本番環境への再移行
という一連の流れをすべてやり直すことになり、納期にも大きく影響してしまいました。
▶ 何を学んだか
この件を通して、「工程ごとの合意」と「関係者の可視化」の重要性を痛感しました。
確認が取れていると思っていても、「誰が見たか」「最終的に誰が決めるか」が曖昧なままだと、途中で方針が揺らぐリスクが大きくなることを実感しました。
特に印象的だったのは、クライアント側の担当者が「私はこれでOKだと思っていたけれど、部長の意見は聞いていなかった」という言葉。
この一言で、「確認してもらったつもり」では不十分だと学びました。
その後、私たちは「確認者一覧表」を用意し、関係者とその役割を明文化。各工程で誰がOKを出すのかを明確にするようになりました。
- プロジェクト開始時に最終確認者を明確にする
- 各フェーズで「確定ポイント」を設け、文書化する
- 大幅な変更があった場合、追加費用・納期再調整が必要である旨を事前に説明する
こうしたルールを整えたことで、クライアント側でも社内調整の重要性に気づいていただき、よりスムーズに進行できるようになりました。
納期がずれてしまった
▶ 何があったか
案件を進める中で、社内外の連携やクライアントとのやり取りに時間差が生まれてしまい、想定していたスケジュールよりも納期がずれてしまいました。
制作側としても状況を把握しているつもりではありましたが、「今、誰がどのタスクを止めているのか」が明確でなかったことが、遅延の引き金になったと感じています。
▶ 何を学んだか
原因は「見える化の不足」だけではありませんでした。
プロジェクトは“チームスポーツ”なのに、当時は個々のタスクを自分で把握していればOK、という意識が強すぎたのだと思います。
また、クライアントに対しても「お忙しいだろうから連絡を控えていた」ことが、かえって全体の進行を遅らせていました。
この経験から、「進行の主導権は私たちが持つべきだ」と考えるようになり、今では毎週、全案件の進捗確認と担当者からの報告を行う運用に切り替えました。
- 毎週月曜日に全案件の進捗を確認
- 各担当者が現状を報告し、ズレや課題を早期に共有
- 遅延やボトルネックを見える化し、調整に活かす
全員が同じページに立ってプロジェクトを進められるようになったのは、大きな前進です。
KPT法の活用:小さな改善を、確実に積み上げる
私たちは、プロジェクトごとの振り返りKPT法(Keep/Problem/Try)を取り入れています。
目的は、メンバーの業務負荷やストレスを軽減し、より円滑な制作環境をつくること。日々の気づきや小さな違和感、問題点を継続的に記録することで、改善のサイクルを回し続けています
KPTミーティングの運用ルール
タイミング:案件終了から1週間以内に30分〜1時間のミーティングを設定
記録内容:担当者・業務フェーズ・気づき・カテゴリ(K/P/T)・コメント等を記録
目的:属人的なノウハウをチームの資産に変えること
継続することで見えてきたこと
たとえば、ある案件では「クライアントからの資料提出が遅れがちだった」ことが課題だったため、Tryとして「納品日を先に設定し、逆算してリマインドを送る運用」に切り替えました。
その結果、資料提出の遅れが大幅に減少し、次回以降はその取り組みをKeepとして定着させることができました。
こうしたサイクルを続けることで、チームとしての改善力や柔軟性が着実に育ってきていると感じています。
失敗に向き合い、変化し続ける組織でありたい
失敗は、なかったことにしてはいけないと私たちは思っています。
その一つひとつに向き合い、仕組みで見直し、次に活かせるようにすることで、組織は強くなると信じています。
これからも「問題があればすぐに共有し、次に進める」チーム文化を大切にしながら、お客様とともに、より良い未来をつくっていきたいと考えています。
私たちは、「経費」ではなく「投資」に導くホームページ制作会社です。
ホームページはあくまでも手段の一つです。かっこいい、可愛いやおしゃれは重視されがちですが、その先にある目的を達成することがより大切だと考えてます。その先にいるのは誰で、なんの悩みをもっているのかを日々考えています。
ホームページをリニューアルを考えられてる方、ホームページを誰に頼んでいいかお困りの方、是非パインズアップをご検討ください。
ホームページの無料相談
「ウェブ専任の社員はいらないけれど、何か問題が発生したときに気軽に相談できるウェブ担当を外注できればいいのに」という声から始まった企業のWEB運用をサポートするサービスです。
・TANTOU